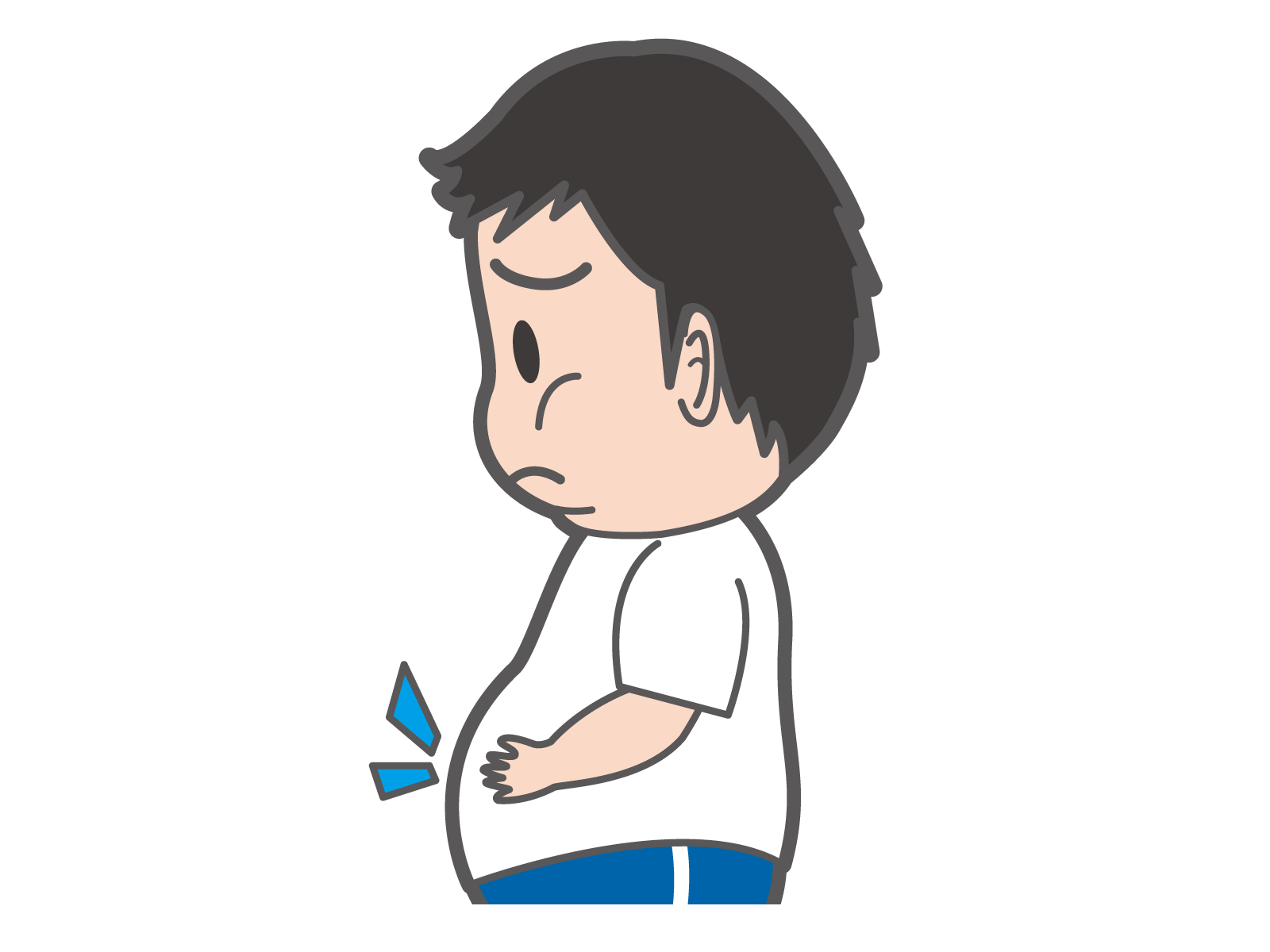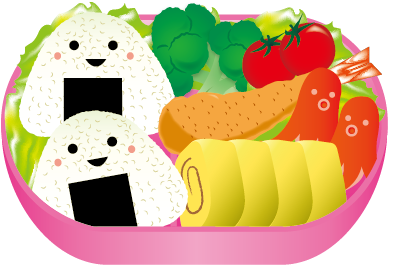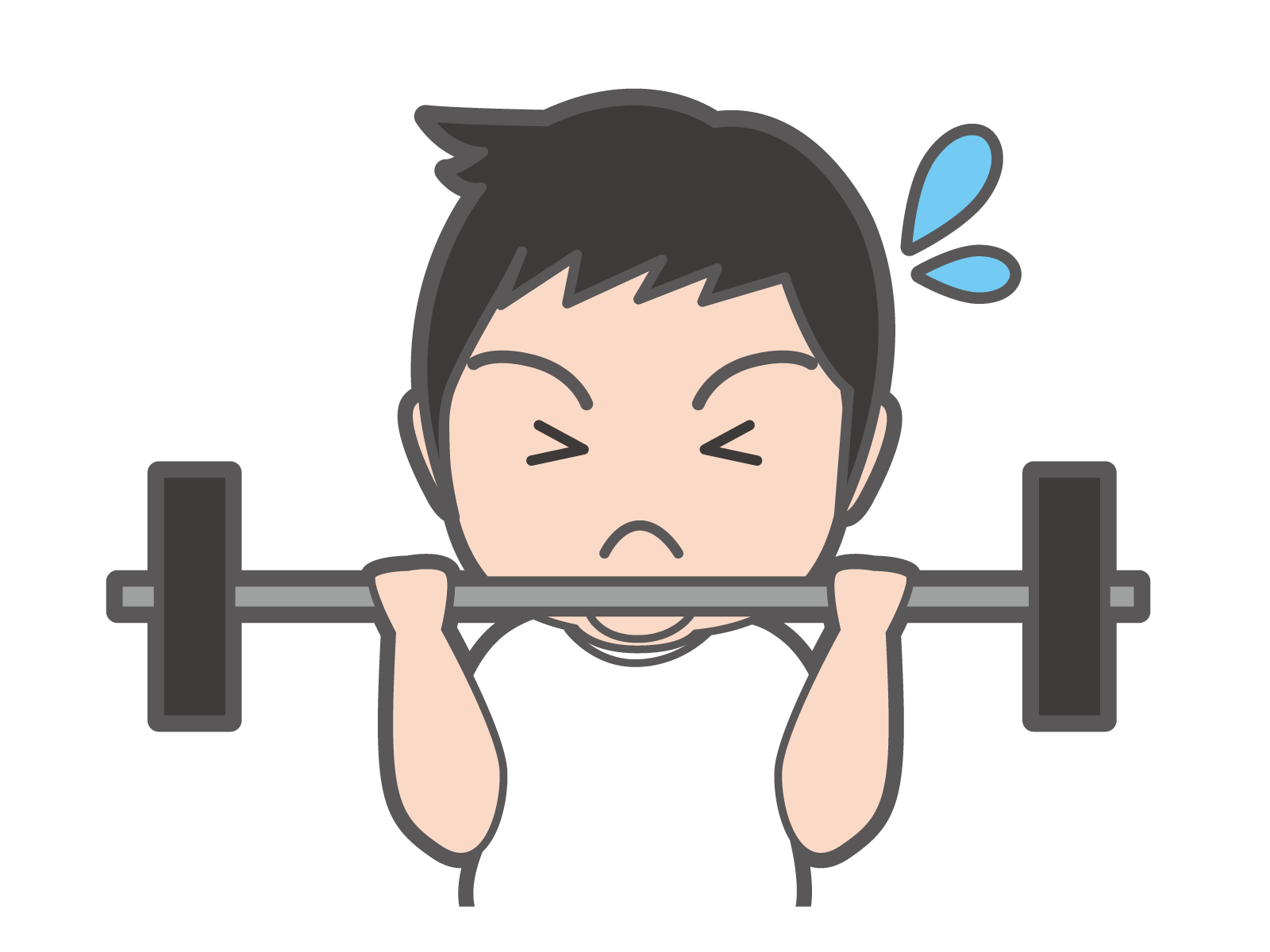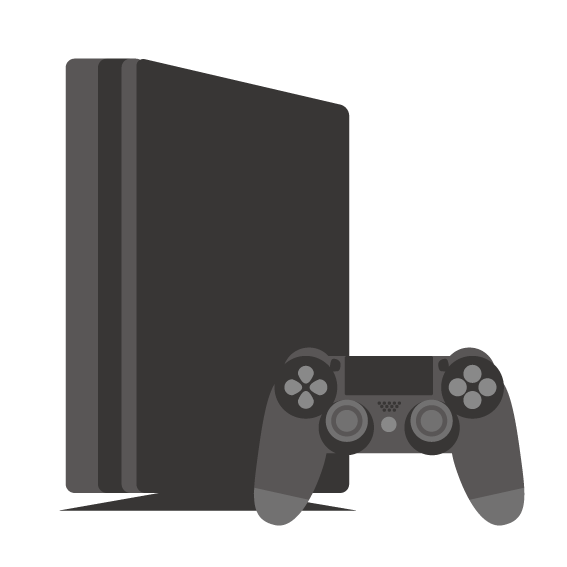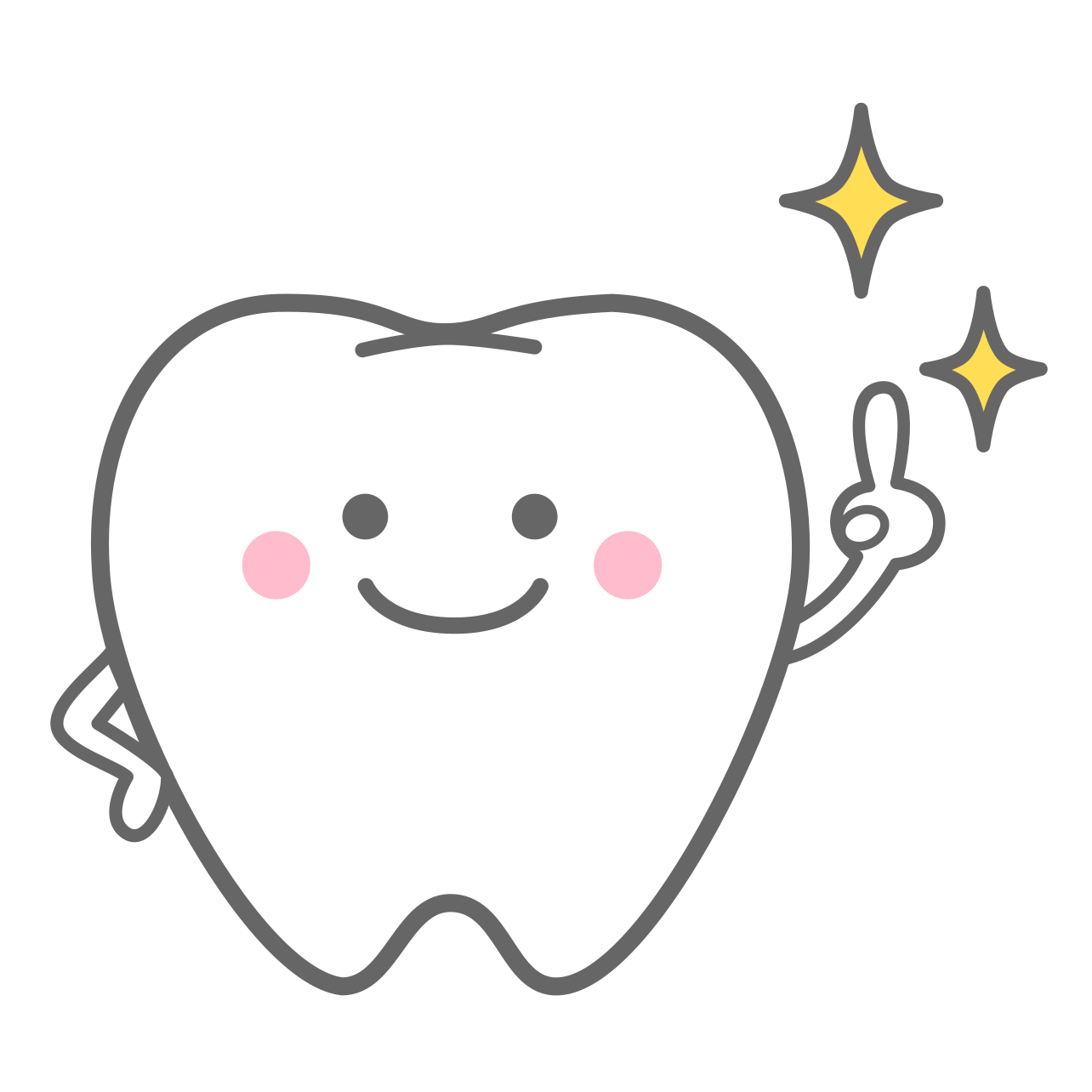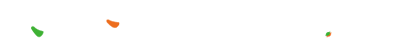春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
さて今月の【健康づくりWEBかわら版】をお届けします!
生活習慣が原因でおこる「生活習慣病」ですが、今や大人だけでなく、子どもにも身近なものとなっています。予防には食生活をはじめとする子どもの頃からの生活習慣がとても大切で、その先の一生の健康を左右するともいわれています。
そこで今回は『小児生活習慣病』に関するお話です。
現代では小児肥満が増加し、糖尿病や高血圧、動脈硬化などの生活習慣病になる子供たちが増加しています。その主な原因は日々の食生活で脂肪分や糖分を摂りすぎていることや、身体を動かす機会が減っていること、そして受験などのストレスです。
文部科学省の調査では、1970年~1999年の約30年間で肥満児の数が2~3倍、思春期世代では約1割が肥満状態にあるとわかっています。
今はまだ発病していなくても、今のままの生活習慣を継続していると20代、30代で発病する可能性が高まり、重症化や若年死する危険があります。
小児期メタボリックシンドロームの診断基準(6~15歳)
小児肥満の子どもの70%は成人肥満に移行すると考えられています。また、小児期に肥満度が高い場合、メタボリックシンドローム(血圧・血糖・中性脂肪の上昇、HDLコレステロールの低下など)を発症している可能性も高くなることがわかっています。
厚生労働省による小児期メタボリックシンドロームの診断基準は次のとおりです。(1)を満たした上で、(2)~(4)を2つ以上含む場合、小児メタボリックシンドロームと診断されます。
- ウエスト周囲径
中学生80㎝以上/小学生75㎝以上、
もしくは ウエスト周囲径(cm)身長(cm)=0.5以上
- 中性脂肪:120mg/dl以上
かつ/または HDLコレステロール:40㎎/dl未満
- 収縮期血圧(上):125mmHg以上
かつ/または 拡張期血圧(下):70mmHg以上
- 空腹時血糖:100mg/dl以上
「三つ子の魂100まで」ということわざがありますが、子どもの肥満も3歳までに決まるといわれています。食習慣では食事時間がバラバラ、甘い飲み物を飲む、野菜をあまり食べない、スナック菓子などをよく食べるなど、肥満の原因となる習慣がついてしまい、肥満になる体質が決定してしまうということです。
≪子どもの生活習慣病危険度チェック≫
- 甘い飲料をよく飲む
- 夕食や就寝時間が遅く、朝食を欠食する
- カップ麺やファストフード、スナック菓子をよく食べる
- 脂っこいものが好き
- あまり運動をしない
- 受験などの強いストレスがある
- 両親のどちらか、または両方が太っている
- よく噛まず、早食いである
チェックに当てはまる人(子ども)は、生活習慣病のリスクがあります。
生活習慣は両親から引き継がれることが多く、子どもが肥満の場合、親も同じように太っていることが多いといわれています。
また、肥満だけでなく痩せすぎも身長の伸び悩みやホルモンバランスの乱れなど成長へ悪影響を及ぼすリスクがあり、注意が必要です。
子どもの頃に備わった食べ物の好みや生活習慣は、そう簡単に変えられるものではありません。そこで、まずは大人が生活習慣病の予防のため、そして子どもの未来の健康のために、家族で出来ることから取り組んでいきましょう。
①食事
1日3食規則正しく食べることが大切です。そして、食物繊維が豊富で噛み応えのあるごぼうなどの根菜類、小魚、豆など和食を中心とした食事を心掛けましょう。
②運動
エスカレーターをやめて階段を利用する/30分早起きして親子でラジオ体操や散歩、縄跳びをする/キャッチボールをするなど、親子で運動をするための時間をつくりましょう。親子のコミュニケーションは、ストレス解消などにも効果的です。
③テレビの視聴時間・テレビゲームの時間
テレビを見ている時間が長い人は、肥満の人が多いことがわかっています。運動不足になりやすいことや、テレビの視聴時間が長いほど、CMに出てくる菓子を食べる傾向にあるなどの調査もあります。視聴時間は1~2時間程度とし、長時間見ないようにしましょう。
④睡眠
睡眠時間が短くなると、夜間の脂肪の分解が抑えられます。また、睡眠不足が続くと、日中やる気がでない、運動する気になれない、などの抑うつ的な状態になることもわかっています。
早寝早起きを心掛けましょう。
⑤口腔
よく噛んで食べることで脳の活性化や唾液分泌の促進、満腹中枢を刺激し肥満の予防するなど、さまざまな効果があります。
子どもの頃からよく噛み口周りの筋肉やあごの骨を強くする/虫歯や歯周炎を予防し、左右でバランスよく噛めるよう定期的に歯科にチェックしてもらうなどで、口の健康を保ちましょう。
子どもの生活習慣のうち、夜食の摂取頻度やテレビの視聴時間、起床時刻は両親の生活と関係があることがわかっています。
よって、子どもの生活習慣病の予防には、両親の協力がとても大切です。食事や運動、生活スタイルなどを今一度見直し、子どもの未来の健康を守っていきましょう。
※今回の記事は次の資料を参考・引用して作成しました。
・厚生労働省HP、文部科学省HP
・健康salada
・e-ヘルスネット
一般財団法人日本予防医学協会
HP https://www.jpm1960.org/
本メールマガジンに掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。
Copyright (c) The Association for Preventive Medicine of Japan.
All rights reserved.
|
- 健康診断業務の代行はお任せ!健康管理業務のお悩み・お困りごとは日本予防医学協会にご相談ください -