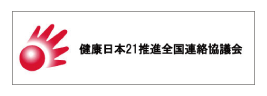聴力検査

会話法聴力、または選別聴力検査として1000Hz(低音域)と4000Hz(高音域)の聴力を調べます。
会話法聴力
「会話法」は診察の際に医師との会話のやりとりの中で聴力を確認し、支障がなければ「異常なし」と判断されます。
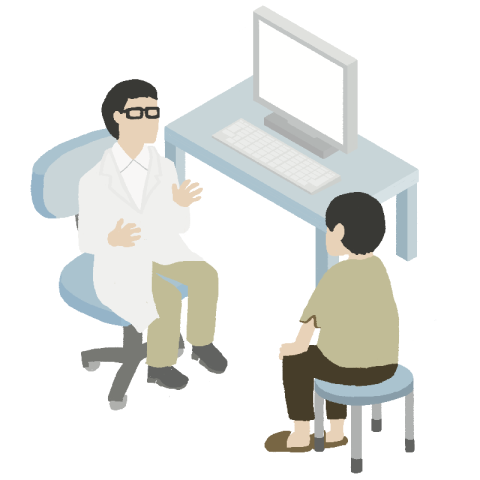
選別聴力検査
選別聴力検査では、左右各耳について、検査ブースでヘッドフォンを装着して音が聞こえるかどうかを検査します。
健診では、自分で気が付かない難聴を指摘されることがあります。その時点で耳鼻咽喉科に受診し精密検査を受けることで、難聴の程度やどの部位が原因なのか、また必要な対応は何か早期に指導を受けることができます。
Q&A
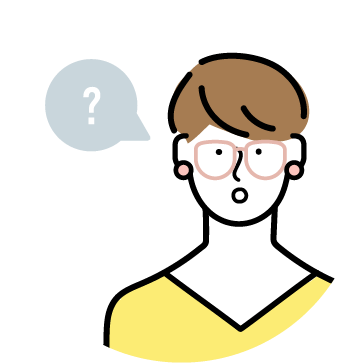
生まれつき耳が聞こえません。検査する必要はありますか。

先天的、あるいは後天的に耳が聞こえない方は聴力検査を実施しませんのでお申し出ください。
同様に、片方のみ聞こえない方は聞こえる側の耳のみ検査をおこないます。
同様に、片方のみ聞こえない方は聞こえる側の耳のみ検査をおこないます。

補聴器を使っていますが聴力検査はできますか?

補聴器を使っている方も通常どおり聴力検査をおこないます。ただしハウリングが起こってしまう場合があり、その場合には検査を中止します。

去年の健診で結果が悪かったので医療機関を受診したが、加齢のせいと言われました。今年も結果が悪かったのですが加齢のせいなんですよね? 医療機関を受診しなくてもいいですか?

健康診断の結果はあくまで健診当日のお体の状態をお知らせするもので、聴力検査結果に異常があれば要精密検査(G2)の判定になります。加齢以外の理由で異常が発生していないことを確認するためにも、受診をお勧めします。ただし、耳鼻科で加齢影響等による継続的な聴力異常と診断されていて病歴問診で経過観察中または通院中と回答された場合は、経過観察中(B2)や加療中(C2)の判定となります。
検査結果の見方