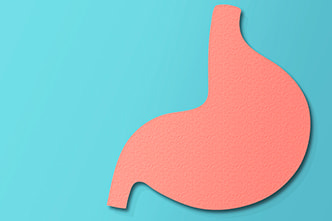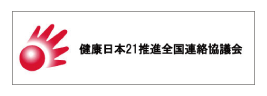一般財団法人日本予防医学協会では、企業・健康保険組合に向けた健康診断を受託しています。
このページでは、当会が受診者様、健診ご担当者様にご報告している下記の健診結果に関して説明しています。
- 受診者さま宛の健康診断結果(健康診断レポート)
- 健診ご担当者さま向けの健康診断レポート控え(個人通知)
- 健診ご担当者さま向けの健康診断結果報告書、要管理者一覧表、受診者一覧表(ホチキス留めしてあるもの)
- 健診ご担当者さま向けの健康管理台帳 等
健康診断の委託先や、健康管理業務のお悩み・お困りごと、ご相談ください!→日本予防医学協会のサービス
胃部レントゲン検査
胃部レントゲン検査は、造影剤(バリウム)を飲み、上腹部にX線を照射して、食道から胃、十二指腸までを観察します。
臓器の形や異常(炎症、潰瘍など)を調べる検査です。
異常が発見された場合の精密検査としては、上部消化管内視鏡を行うのが一般的です。
| コード対応表 | 胃部X線検査の所見は日本語表示の他にコードで表示いたします。 【例:6-0-6(部位1-部位2-所見)は、「十二指腸球部変形」となります。】 |
|---|
| 部位1 | 部位2 | 所見 | 所見説明 |
|---|---|---|---|
| 1.食道 | 0.その他 | 1.硬化 | 胃壁のやわらかさがなく、伸縮性が悪い状態 |
| 2.噴門 | 1.前壁 | 2.壁不整 | 壁・粘膜表面の乱れた状態 |
| 3.胃体部 | 2.後壁 | 3.欠損 | バリウムの陰影が一部写っていない所見 |
| 4.胃角部 | 3.小弯[ しょうわん ] | 4.ニッシェ | 潰瘍等の窪んだ部分にバリウムが溜まった所見 |
| 5.前庭部 | 4.大弯[ だいわん ] | 5.レリーフ異常 | 粘膜のひだの走行が異常な状態 |
| 6.十二指腸球部 | 6.変形 | 正常像に比べ辺縁の形が変わっているもの | |
| 7.穹窿部[ きゅうりゅうぶ ] | 7.充満不良 | 十二指腸球部にバリウムが入らない状態 | |
| 8.幽門 | 8.バリウム抜け | 胃壁の隆起物によってバリウムがはじかれた状態 | |
| 9.十二指腸 | 9.バリウム斑 | 粘膜の凹んだ部分にバリウムが溜まった所見 |
胃部内視鏡検査
口や口から内視鏡(胃カメラ)を入れて、食道、胃、十二指腸を直接観察する検査です。 胃十二指のポリープ、潰瘍、がんなどが発見できます。病変がみつかった場合、その一部を採取し病理組織検査をおこなうこともあります。
検査で病変がみつかった場合に、その一部を採取(バイオプシー)して、頭微鏡で観察し、良性か悪性かを判断する検査を「病理組機検査」といいます。胃病理組織検査では結果を5段階に分けて評価しています。数字が大きいほど、悪性度が高くなります。
胃がんリスク層別化検査(ABC検診)
胃がんリスク層別化検査(ABC検診)は「ピロリ菌感染の有無を調べる検査」と「胃粘膜の萎縮度を調べる検査」を組み合わせて胃がんになるリスクを分類する検査です。
ABC判定区分は下記の表のとおり、A~D群に分類され、今後の管理・対処法が決まります。
| <ABC判定区分> | ヘリコバクターピロリ菌の感染有無 | ||
|---|---|---|---|
| (-) | (+) | ||
| ペプシノーゲン法 (萎縮度) |
(-) | A群 | B群 |
| (1+ ~3+) | D群 | C群 | |
※スマートフォンなどで表の右側が表示できない場合は画面を横にしてご覧ください。
| ABC判定区分 | 判定説明 | 判定 区分 |
|---|---|---|
| A群 | ピロリ菌感染・胃粘膜萎縮はいずれも否定的で、胃がんになる危険性が比較的低いと考えられています。 | A1 |
| B群 | ピロリ菌に感染している疑いがあります。胃粘膜の萎縮は軽度ですが、胃潰瘍・胃がんになる危険性を否定できないので、ピロリ菌を除菌し定期的に画像検査等を実施することが望ましいです。 | G2 |
| C群 | ピロリ菌感染および萎縮性胃炎があります。胃がんになる危険性があるので、ピロリ菌を除菌し定期的に内視鏡検査を実施することが望ましいです。 | G2 |
| D群 | 高度の胃粘膜萎縮がありピロリ菌が住めない状態です。胃がんになる危険性が相当に高いので、年1回以上、内視鏡検査を行い注意深く経過を観察する必要があります。 | G2 |
検査対象外となる方
ABC検診を受診しても正確な判定結果が出ないため、検査実施対象外となります。
①ピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方
②食道、胃、十二指腸の疾患が強く疑われるような自覚症状がある方
③食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの治療を受けている方
④胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬※)を飲んでいる方(薬を服用中もしくは2か月以内に服用していた方)(プロトンポンプ阻害薬※:オメプラール、タケプロン、パリエット、ネキシウムなど)
⑤胃の切除手術を受けたことがある方
⑥腎不全または腎機能障害がある方(目安:クレアチニン値3mg/dl以上)